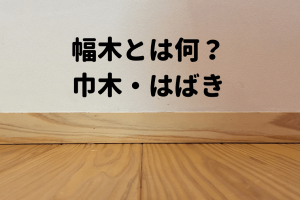この記事では
- 「上棟とは、具体的にどういうものですか?」
- 「上棟の流れはどうなんだろう?」
- 「上棟のお祝いって、どうすればいいですか?」
- 「上棟の差し入れって、必要なのかな?」
- 「上棟って、どれくらいの時間がかかるのかな?」
- 「上棟に立会いたいんだけど、どうかな?」
といった疑問にお答えします。

目次
上棟とは?
新築一戸建て住宅の家づくりをお考えでしたら、一度は「上棟」というフレーズを聞いたことがあるのではないでしょうか。上棟は別名「棟上げ(むねあげ)」や「建前(たてまえ)」「建方(たてかた)」とも言われます。
木造建築において、棟木(むなぎ)を取り付けることを指します。棟木とはどこの部分を指しているかと申しますと、住宅の屋根の頭頂部の木のことです。

上棟にかかる時間
上棟にかかる時間についてですが、今どきの木造住宅を建築する際は、大体1-2日程度で上棟してしまいます。
ですから、なかなか実感がわきませんけれども、かつての日本の住宅は取り掛かってから、上棟するまでに長い期間がかかりますので、それをお祝いするという儀式的な側面もあったようです。
また、現在では木造軸組工法という木造住宅以外にも、軽量鉄骨造などの住宅がありますが、これらの木造以外の住宅の場合、「上棟」という行為自体はないのですが、基本構造の骨組みが完成したことを上棟と表現することもあるようです。
上棟式とは何ですか?
上棟式とは、この上棟(つまり、骨組みが完成するとき)時に行う儀礼です。
一種の建築儀礼です。地鎮祭なども現在でも行われている建築儀礼です。
この上棟式の意味を一説には、家の魂を祝い込めるものであったと言われています。
近い意味として、別の説では、新築の家を守ってくれる神霊をしっかりと棟に叩き込もうという儀礼だと言われています。
概ね、上棟式には神や霊魂を降ろし、棟木を叩いて入れこむことで、その家の守護神とするような儀礼だと思われます。
新築の家が完成した後は、棟木を通して神霊が降りてきます。
その家に神棚がない場合、神霊は小屋裏(屋根裏)に常在するものと考えられていました。家に神棚がある場合、高所にある神棚の神札を依代(よりしろ)として、そこの常在するものと考えられていました。
このように日本人の価値観と住まいには、密接な関係を持っていたわけです。
日本にはその歴史と同じだけ、住まいの歴史があります。
上棟で雨の場合、大丈夫ですか?中止・延期になることも当然あります

上棟の際、天気が雨の場合、不安になります。上棟はオープンエアのなかで、構造の木を組み上げていくことになります。
一般的には雨の程度によります。
そのため、上棟を行う日が天気予報でかなりの雨が降るというのが予想された場合は上棟自体を中止・延期することになることも当然あります。雨がザーザー降っているなかで、クレーン作業や高所作業をしたら危ないですから。
ただ、多少の雨、雨量の少ない雨であれば決行することも多いです。その際に「柱」「梁」などの「構造木材が濡れると、家の強度に問題が・・・?」と思われるかもしれませんが、木材は雨に濡れても乾燥しますし、強度は変わりません。一時的な雨の影響は気にされることではありません。
上棟の際に雨で濡れるということに関しては、乾燥すれば特段の問題はないです。昔の住宅建築は現代のように数か月で完成というスピードではなかったですので、数カ月雨ざらしということもあった時代もありました。
その点、現代の住宅建築はスピードが早く、雨にさらされる時間も短いです。
上棟日の一日を解説

上棟日は吉日かどうか。また、大工さんたち(応援に来てくれる大工さんも多いので)、木材の業者、クレーン屋さん、屋根屋さんなどなど、色々な方々のスケジュールを合わせないといけないので調整する必要があるためです。それで決定します。
上棟の日はかなり前から段取りされます。
上棟日の決め方
上棟日は住宅建築の節目となる日になりますが、こうしたイベントの日については六曜でよく検討されます。
六曜(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)のなかでは、大安、友引、先勝、先負といったところが吉日と言われています。また、三隣亡(さんりんぼう)は向こう三軒まで災いが起こるといわれているので避ける傾向にあります。
7時・7時半:大工さんたちが集合

当日は大工さんが集まります。
人数としましては、4人のときもあれば、6人、8人のときもあります。
今回(写真の建築現場)は大工さんだけで12人来ていただきました。集合時間は7時や7時半くらいでしょうか。事前打ち合わせの時間になります。
8時:上棟・工事のスタート

実際のスタートは午前8時くらい。
工事の安全など、挨拶をしましてスタートします。危ない作業もありますので、安全第一ですね。
スタートからはいきなり上棟という名のような棟木を上げるようなことはありませんでして、1階の柱を立てます。何本も立てていきます。
家がナナメに傾いてはいけませんので、柱の垂直を見ながら補正しまして、固めていきます。
10時:休憩
10時に最初の休憩です。
やはり大変な肉体労働になりますから、きちんと休憩しないとバテます。
夏は気温が高く、過酷な作業になります。
12時:昼食
12時、正午になれば、昼食です。
建主様・施主様のお気持ち次第ですが、大工さんたち含めて業者人数分のお弁当をご用意される方もいます。
これらの差し入れについては後程詳しく解説します。
13時:工事再開
13時にお昼休憩が終わりまして、工事再開です。
柱が立ち、梁(はり)や桁(けた)といった横架材と呼ばれる横方向の木を置きまして、建物の構造をくみ上げていきます。
2階の床下地合板も貼ります。

そうやって、2階の柱を立てていきまして、同じように横架材を掛けまして、屋根下地へと行きます。そうして、ようやく棟木が上がります。事実上の「上棟」です。
実際上のオペレーションとしましては、そこから屋根下地の合板を貼ったり、ルーフィングをしたりと、次の工程をできるかぎり進めていく流れになります。
15時:休憩
15時に最後の休憩に入ります。
後半戦なので、かなり疲労がたまっています。
17時すぎ:上棟日の終わり
大体、17時すぎには上棟日が終わります。
もう少し遅くまでする場合もあります。
概ね、このような流れを上棟と呼びまして、上棟日に行われることです。
午前8時スタートで、午前10時に休憩、正午に昼食、午後3時に休憩、午後5時終了というのが一日のリズムになります。

朝8時から夕方午後5時くらいまで、丸一日がかりで、ようやく一通り終わるくらいで、いささか大工さんにとっては大変な一日になります。
上棟式は今ではしないほうが大半。上棟のお祝いの実際

そもそもの話なのですが、現在の注文住宅業界では上棟祝いや上棟式といった儀式がなくなってきている傾向にあります。
ですから、「そもそも上棟祝いを渡すタイミングがない」です。
たしかに昔は神主を招き、神事を行い、親戚・ご近所を集めての餅まきや祝い事をしていました。
ただ、現在では大半の住宅会社で上棟式といったイベントをすることはなくなってきています。
特に全国的に知名度の高い大手ハウスメーカーは上棟式といったイベントはしない方針だそうです。
上棟式がなくなってきている理由とは?
上棟式がなくなってきている理由としては「上棟式自体が時間がかかるため、人件費がかかり、工期遅延につながるから」です。また、「上棟式の日程を調整することが必要なため、工程や業務上の支障が出やすいから」です。
実際、人件費や工期遅延、工程管理の業務上の問題になることは多いです。
現代の注文住宅業界では上棟式自体が減ってきているのは当然な流れです。
ただ、せっかく自宅の建築をしてくれるわけですから、大工さんや職人さんたちに直接感謝を示したり、親睦を深めることは好ましいかな、と思います。
ですから、住宅会社・工務店・ハウスメーカーなどの住宅建築の依頼先に「上棟式をやりたい(やったほうがいいのか、も含めて)」「ご祝儀を渡したほうがいいかどうか」など確認されてみることをおすすめします。
上棟式・上棟のお祝いの実際はこんな感じ。上棟の立会いをするくらい

「上棟式をしたいけど、できない」というほどの強制力ではない工務店・注文住宅会社が多いです。そのため、建主様・施主様の希望があれば上棟式を行われます。
ただ、そういう場合でも、かつてのような神主を招いての神事、親戚一同が集まっての宴会といったかたちはほぼほぼ見られません。
実際としては、簡易的なかたちで、上棟式といった式ではなく、棟梁や大工さんへのお昼(お弁当)をふるまい、見学して、お祝いで手土産とご祝儀を渡して帰るといったかたちをとられることが多いです。
上棟祝いはどうすればいいですか?ご祝儀は?

現代の簡易的な上棟式は前述した通り、下記のようなものです。
「棟梁や大工さんへのお昼(お弁当)をふるまい、見学して、お祝いで手土産とご祝儀を渡して帰る」
です。
ここでは実際に具体的な上棟式のお祝いやお礼、ご祝儀などの内容についてご紹介します。
上棟式のお祝い・お礼の具体的なリスト
上棟式のお祝い・お礼の具体的なリストは下記のようになります。
- 棟梁や大工さんなど業者の人数分のお弁当
- 休憩用の缶コーヒー、お茶、ジュース、お菓子
- ご祝儀
- 業者人数分の手土産
余談ですが、住宅業界の職人さんたちはなぜか、缶コーヒーをよく飲むんです。僕もなぜかまではよくわからないのですが、缶コーヒーを愛してます。ですから、休憩用に差し入れされる場合は缶コーヒーを入れておくと喜ばれる可能性は高いです。
上棟の差し入れ(お弁当・お茶・お菓子)を詳しくご紹介
上棟の差し入れは前述の通り、「棟梁や大工さんなど業者の人数分のお弁当」「休憩用の缶コーヒー、お茶、ジュース、お菓子」です。
この上棟の差し入れについて詳しくご紹介します。
上棟のお弁当はどんなものがいいですか?
「棟梁や大工さんなど業者の人数分のお弁当」を差し入れすることになると思うのですが、気になるのは「上棟のお弁当はどんなものがいいですか?」というところでしょう。
はっきり申し上げれば、建主様・お施主様の気持ち次第なので高いものでも安いものでもかまわないです。
いいお弁当ですと、仕出し弁当という感じです。
比較的安価にすむお弁当は「ほっともっと」「ほっかほっか亭」といったお弁当チェーンストアの幕の内弁当クラスです。
上棟の差し入れお茶・お菓子はどんなものがいいですか?
上棟の差し入れに入れるお茶は前述したとおり、缶コーヒーやペットボトルお茶、ペットボトルのジュースです。
ペットボトルの2Lものに、紙コップがあると、人数が多くても対応できるので便利です。
しつこいですが、缶コーヒーはあるといいです。
お菓子は甘いもの、塩気のあるものをセレクトしていくといいです。
何でもいいです。スーパーマーケットで、よさそうなお菓子、せんべいなど、小分け袋に入っているものが人数多くても対応できるので便利です。
上棟のご祝儀の相場はいくらくらいですか?
上棟に際して、ご祝儀を渡される建主様・施主様はその相場が気になるところでしょう。
そこも正直、建主様・お施主様の気持ち次第なので決まった金額はありません。
あくまで参考の金額ですが、
- 現場監督・棟梁:1万円程度
- 応援の大工さん・その他職人さん:5,000円程度
このあたりが目安です。
もちろん、余裕のある方であれば、多いにこしたことはないですから、5万円、10万円とお渡しいただいてもかまいません。多いほうが喜びます。
上棟の手土産はビールが定番
上棟式のお祝い・お礼の最後は「業者人数分の手土産」です。
では、手土産として一般的なものは何かと聞かれますと「ビール」が定番です。
お酒を飲まない方もいますので、全員ではないのですが、一般的にはお酒を好む方が多い業界ですから、ビールであればハズレはないです。
ビールであれば、飲まない方も他の方に渡せますし。
上棟式での挨拶・会話、何を話したらいいですか?
上棟式や上棟日で、住宅会社の方や工事業者さん、棟梁・大工さんに挨拶したり、会話したりするでしょう。そういう場合、何を話したらいいのかな?と思われるかと思います。
そういった場合は、現場で汗かき、大変な工事をされる工事業者さんには感謝を述べたり、残りの工事が無事、事故なく進むことを願う気持ちを素直に伝えられることをおすすめします。
上棟式の予算はいくらぐらい?
上記のようにお祝いやご祝儀、手土産といったものでお金を使いますから、上棟式に予算としていくらぐらいを想定しておけばよいかといいますと、ざっくり「10万円程度」かな、と思います。
上棟式そのものにどこまでお金をかけるかでも変わりますが、基本的にはご祝儀、手土産、差し入れといったところです。
昼食の棟梁・大工さんなど業者さんのお弁当で1.5万円。差し入れの休憩用の缶コーヒー、お茶、ジュース、お菓子で1万円。ご祝儀で6万円。業者人数分の手土産で1.5万円。合計して10万円といったところになります。
これは「こうしなければならない」という類の話ではなくて、弁当差し入れなければ-1.5万円ですし、ご祝儀も上棟に参加する人数次第で金額は変わります。手土産も人数次第。
そういうわけで、予算的には10万円程度を想定されるのが好ましいですが、少なくてすむ場合も多いでしょうし、また、奮発して多く支払うのもアリかもしれません。
上棟についてのまとめ
このようなかたちで、上棟という、新築一戸建て住宅では大事な一つの区切りを迎えます。
上棟式そのものはなくなっていく傾向にありますが、家づくりのひとつの区切りとしてわかりやすいタイミングです。
もちろん、お金がかからないわけではなく、きちんとしたものにしようと思えば、やはり10万円程度のお金がかかると想定されますから、支出は否めませんが、快い家づくり・住宅建築をする上ではやっておいて損はないかな、と思います。
素敵な上棟、楽しい上棟式は思い出に残りますし。
関連:餅まきって、どういうもの?【餅まきの由来?餅やお菓子は?費用はいくら?】