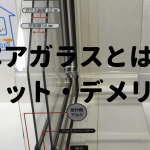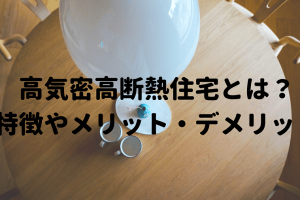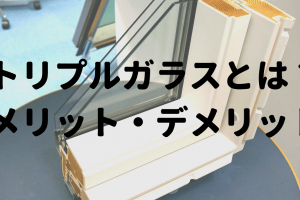目次
浄化槽とは排水をきれいにする設備のこと
下水道設備が整っている地域では、排水処理は特に問題はありません。
しかし、中には下水道設備が不十分な地域も存在します。
浄化槽とは、そのような下水道が設備されていない地域で、汚水を含む一般の生活排水を公共用水域に排出する場合に、それらを処理するために必要な設備です。
この設備をつける理由は、浄化槽によって浄化処理した下水しか放流することができないからです。また浄化槽には、雑排水と汚水の両方を浄化できる機能が求められます。
なぜ、浄化槽が必要になるのですか?
住宅などの建物で使用された水や湯は、通常汚れた状態で排水されます。
その排水を川や海などに排出する場合は、水質汚濁を防止するために建物内で処理してから排出しなければなりません。
また公共下水道に排出する場合でも、水質によっては下水管路や終末処理場などの下水道処理施設に損傷を与える可能性があります。それを防ぐためには、ある程度の排水処理を行って水質を改善させなければなりません。
排水処理の方法は3つ
排水の処理方法としては、大きく3つの方法が挙げられます。
1つ目は生物の代謝反応により汚濁物質を分解する生物処理です。
2つ目は酸化や中和のような化学反応を利用して凝集させる化学処理です。
そして3つ目は沈殿や浮上などの物理的な現象を活用した物理処理です。
これらの処理方法でも中心となるのが生物処理であり、活性汚泥法と生物膜法とに分類されます。
活性汚泥法と生物膜法
活性汚泥法は、ばっ気槽内に形成されて浮遊している微生物フロック(活性汚泥のこと)が流入する汚水と空気とを十分に混合・撹拌する間に、汚水中の有機物を吸着・酸化し、次の沈殿槽で活性汚泥が沈殿分離して、上澄み水を処理水とする方法です。
ばっ気槽とは、排水処理などの過程で空気を吹き込み、微生物フロックの微生物を活性化させて排水するタンクのことです。
また生物膜法は、ろ材などに汚水を接触させて、ろ材などの表面に付着している微生物の働きによって、汚水中の汚濁物質を除去する方法です。ここで使われる微生物は、厚みを持った生物膜となっています。
浄化槽の大きさで建物の配置が変わります
浄化槽とは自由に設置できるものではなく、処理対象人数算定して規模や容量を決めなければなりません。
処理能力は建物床面積の合計や世帯数で算出されます。
130平方メートル以下であれば5人用浄化槽、130平方メートルを超えれば7人用浄化槽となります(2019年7月時点)。
また二世帯住宅の場合、風呂や台所は2ヶ所あるとみなされるため、10人用浄化槽として考える必要があります。
場合によっては乗用車の大きさ程度の浄化槽が必要となることがります。浄化槽の上に建物を建てることができないため、浄化槽の位置を先に決めてから住宅の位置を決めることをおすすめします。
公共下水道の位置と浄化槽の位置と大きさを決め、それから建物の形を考えると合理的な住宅設計ができるのです。
浄化槽の仕組み
浄化槽は生物処理である活性汚泥法を利用し、嫌気濾床層と接触ばっ気槽、沈殿槽と消毒層から構成されています。
雑排水や汚水が流入すると、嫌気濾床層で有機物が分解されます。
次に接触ばっ気槽で、酸素が好きな微生物によって水を浄化させます。
浄化された水は沈殿槽に送られ、そこで微生物のかたまりやゴミを沈殿させていきます。
最後に消毒層で塩素剤を用いて水を浄化し、公共下水道に放流します。
嫌気濾床層には、嫌気性微生物を床に敷いた小石のような材が置かれています。
また、接触ばっ気槽には好気性微生物が設置してあります。
嫌気性微生物とは、酸素を必要としないバクテリアや細菌のことを指します。
好気性微生物とはその反対で、酸素を必要とするバクテリアや細菌です。
浄化槽設置で注意すること
このように浄化槽では微生物が働いて汚物を分解していますが、決められたもの以外を浄化槽に流してしまうと微生物が死滅する可能性があるため注意する必要があります。
また、浄化槽は設置したらそのままずっと放置というわけではなく、年に1回の点検が必要です。