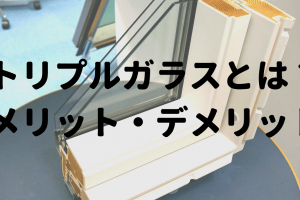- 建ぺい率(建蔽率)とはどういう意味ですか?
- 建ぺい率(建蔽率)はどういう制限がかかるのですか?
この記事ではこのような疑問にお答えします。

目次
建ぺい率(建蔽率)とは?詳しく解説
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことを指します。
建ぺい率は用途地域別に上限が定められており、建物を建てる際には建ぺい率を遵守する必要があります。
建築面積の算出方法は、建築基準法施行令第2条に記載されており、原則として建築物の柱や外壁の中心線で囲まれた部分を求めます。ただし、ひさしやバルコニーなどが中心線より1メートル以上突き出ている場合は、先端から1メートル後退させた部分までを建築面積に加えるため、忘れずに覚えておきましょう。
住宅専用地域に区分される建ぺい率
全部で十二種類定められている用途地域に対し、主に住宅を建てることを目的とした住宅専用の用途地域は七種類存在します。
低層住宅専用の地域には「第一種低層住居専用地域」あるいは「第二種低層住居専用地域」に指定されていることが多いです。
第一種低層住居専用地域には店舗を建てられませんが、第二種低層住居専用地域には、2階建て以下かつ150平方メートル以下の小規模な店舗の立地が認められています。コンビニなどの小規模店舗は、第二種低層住居専用地域に区分されるため覚えておくと便利です。
中高層住宅の専用地域には、「第一種中高層住居専用地域」または「第二種中高層住居専用地域」が指定されています。
第一種中高層住居専用地域には、病院や大学など500平方メートル以下の一定のお店を建てることが可能です。第二種中高層住居専用地域では、病院や大学のほか、1500平方メートル以下であれば物品販売業などの利便施設の立地が認められています。
以上の四地域に対し、建ぺい率の上限は原則として30・40・50・60パーセントの中から都市計画に基づき、特定の値が指定されます。
例外として、防火地域内にある耐火建築物は建ぺい率の制限が緩和され、指定されている建ぺい率に10パーセントが加算されます。
角地にあり、特定行政庁が指定した敷地についても10パーセント加算され、どちらも当てはまる場合は合計で20パーセント上乗せされるため覚えておきましょう。
飲食店や事務所などが混在する住居地域の場合
住居の環境を守るための地域として、「第一種住居地域」と「第二種住居地域」の二つがあります。
第一種住居地域では、店舗や事務所、ホテルなど3000平方メートルまでの建物を建てられますが、道が比較的狭い住宅街や、主要道路沿いに指定されることが多いです。
第二種住居地域の場合、3000平方メートルまでの制限がなくなります。パチンコ店やマージャン店などの遊戯施設を建てることが認められており、商業地域の周辺などに第二種住居地域が指定されます。
飲食店や事務所に加え、自動車ディーラー店などの自動車関連施設が含まれる地域を「準住居地域」と呼び、県道や国道などの幹線道路沿いに指定されます。
住居地域というイメージは持たれませんが、マンションやビルなどが立ち並んでいることが多く、幹線道路からの自動車騒音を緩衝する緩衝用建築物としての役割も果たしています。
「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」の建ぺい率の上限は、都市計画に基づき50・60・80パーセントの中から指定されます。
4種類の住居専用地域と同様の条件で、建ぺい率の制限緩和が規定されていますが、建ぺい率が80パーセントの地域で防火地域内にある耐火建築物の場合、建ぺい率の制限はなくなります。
二つ以上の用途地域にまたがる場合
建ぺい率は用途地域別に定められていますが、二つ以上の用途地域にまたがっている敷地に建物を建てた場合は、計算方法が異なります。
異なる二つの建ぺい率の地域に敷地がまたがっている場合、該当する地域に属する敷地の割合で算出されます。
第一種低層住居専用地域と第一種住居地域にまたがる敷地を持つ場合など、それぞれの建ぺい率を調べておき、正しい数値を導き出せるようにしておきましょう。