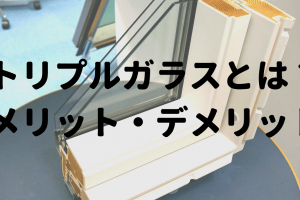目次
そもそもキャビネットって?
キャビネットとは、物を収納する箱型の家具の総称です。そのため、使われる用途・場所によって、いろいろな特徴があり、引き出しタイプや引き戸タイプなど、その形はさまざまです。
もともとキャビネットには「貴重品を保存するための小部屋」という意味があり、ヨーロッパの住居には不可欠の調度品の一つでした。
16世紀頃までのヨーロッパでは、上部に蓋がついた箱型のコッフルと呼ばれる家具が使われていましたが、17世紀になるとキャビネットが登場し、盛んに作られるようになります。
以降、貴重品だけでなく、本や食器をしまうためのキャビネットなども作られ、現在では飾り棚、本棚、食器棚など、いろんな種類の家具がキャビネットと呼ばれています。
キャビネットとサイドボードの違いは?
キャビネットとサイドボードに、それほど大きな違いはありません。
サイドボードはもともと食器などを収納する家具でしたが、今ではリビングでも使われ、用途も広がってきたため、いろんな種類の家具がサイドボードと呼ばれています。
双方とも同じような特徴を持つため混同しやすいのですが、実はキャビネットとサイドボードに明確な違いはないのです。
キャビネットより小型のものをサイドボードと呼んで区別している家具店もありますし、扉付き飾り棚で縦長のものをキャビネット、横長のものをサイドボードと呼んでいる家具店もあります。このように、店舗や人によって、その定義はまちまちというのが現状です。
キャビネットの種類
そもそも箱型の家具全般をキャビネットと呼ぶので、オフィスなどでよく見かける無骨なスチール製のものから、ガラスの扉や装飾が施された木製のアンティーク家具まで、その種類は数多くあります。
主に、日本の家庭で使われるキャビネットの特徴は、大きな箱型で扉のついたものが多く、リビングにあれば本棚、キッチンにあれば食器棚など、その用途もさまざまです。
対してヨーロッパでは、家具そのものも調度品であるという意識もあり、キャビネット自体に装飾や工夫が凝らされています。また、ガラスや陶磁器などの貴重品を眺めるために作られた飾り棚タイプが多く、同じ扉でもガラス扉のものが多いのが特徴です。
そのなかでも、陶磁器を飾るために作られたものは、陶磁器のことをボーンチャイナということからチャイナキャビネットと呼ばれ、扉だけでなく棚板までガラス製で、より中の陶磁器が美しく見えるように工夫されています。
キャビネットの選び方

種類も多く、いろいろな用途に使われるキャビネットを失敗なく選ぶためには、まずはその扉の形状に注目するといいでしょう。
扉のないオープン型
扉がないタイプのキャビネットは、頻繁に使用するものを収納するのに向いています。
日常使いの食器、よく読む本や雑誌、常備薬など、すぐに取り出せるものを収納すると便利です。ただ埃が入りやすいというデメリットもあります。
両開き扉型
オープン型キャビネットと違って、埃が入らないので、頻繁に使わないものの収納に向いています。
また、ガラス扉なら飾り棚としても利用できます。ただし、扉を開けるための十分なスペースを確保する必要があります。
引き違い扉型
扉をスライドさせて開ける引き違い扉型キャビネットには、狭いスペースにも設置できるというメリットがあります。
ただ、オープン型や両開き扉型のように大きく扉を開けることができないため、真ん中にしまったものが取り出しにくかったり、デッドスペースができてしまったりします。
ラテラル型
引き出しタイプのラテラル型は、引き出すことができるので、奥のものが取り出しやすいのが特徴です。
引き出しタイプなので、腰高タイプがほとんどですが、上部がオープン型や両開き扉型で下部がラテラル型のキャビネットなどもあります。