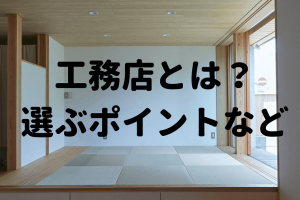家づくりについて調べていくと「諸費用」というフレーズがよく出てきます。
住宅(一戸建て)を新築する、住宅を購入する、
そういうときには、
土地と建物本体のほかに、色々とお金がかかってきます。
その色々なお金のことを「諸費用」と言います。
「諸費用」ですから、「諸」とは「諸々」という意味です。
諸々、色々・・・って、結局、何なんですか?
『諸費用って、結局、どんな費用のことを意味しているのか?』
という疑問が出てきます。
それでは、今回は「新築住宅の諸費用はいくらかかる?家づくりの諸費用まとめ」について、きちんとまとめていきます。

目次
新築住宅の諸費用はいくらかかる?具体的には?
それでは、実際に「諸費用」って何の費用なのか、をまとめていきます。
税金カテゴリ
まずは税金カテゴリでの諸費用をまとめてみます。
結構、税金カテゴリが諸費用のなかでシェアが高いのです。
ちなみに消費税については除外しています。
印紙代・印紙税
印紙代とは収入印紙の代金です。
ひとつひとつは1万円とか6000円とか2万円とかですが、
契約書の枚数が多いので、結構、馬鹿にならない金額になります。
この印紙代は売買契約書や住宅ローンの契約書、
つなぎ融資(ローン)の契約書に添付しなければならないお金です。
いわゆる税金です。
印紙代・印紙税は契約書に記載されている金額によって変わります。
金額が大きいと、印紙代も大きいです。
ただ、建築工事の請負契約書は優遇措置がとられており、低くなっています。
不動産取得税
不動産取得税は不動産を取得した人にかかってくる税金です。
土地も、住宅(建物)も、
どちらも不動産ですから、取得した場合、税金がかかってきます。
自己居住目的の新築住宅取得に際しては、
補助・優遇措置がとられています。
新築住宅を取得した場合は床面積が50-240平方メートル以下ならば、
軽減措置として、建物の評価額から1200万円が控除されます。
登録免許税
登録免許税とは、土地や住宅(建物)といった不動産の登記にかかる税金です。
土地を取得した際、住宅(建物)を取得した際、
「これは自分のものです」と表示(登記)するために税金がかかります。
ちなみに住宅ローンを借りるときに、金融機関から抵当権を設定されるのですが、
この抵当権の設定も登記ですから、税金がかかります。
加えて、この登記業務は基本的には司法書士に依頼することになります。
その司法書士費用は別途かかります。
後述しますが。
固定資産税・都市計画税
固定資産税とは固定資産を持っている人に課せられる税金のこと。
都市計画税とは都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課される税金のことです。
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の土地・建物所有者に対して課される税金です。
不動産所有者に課せられているわけです。
普通は6/15とか、9/29とか、1年の途中で所有権が変わります。
まあ、いつ所有権移転してもいいのですが。
ただ、それでも請求されるのは1月1日時点の所有者ですから、その人が支払うことになります。
売買した場合は、その不動産の元の持ち主(売主)ですね。
ただ、売買して所有権移転した段階で、所有者は買い主(あなた)です。
じゃあ、所有権移転後は買い主(あなた)が所有者ですから、それ以降の税金は負担しなければならないということになります。
そういうわけで、不動産手続きの実務としては、
所有権移転の日(つまり、引き渡し日)を基準に1年365日の日割り計算をした税額を売主に支払うという流れになります。
水道加入金・水道負担金など
水道加入金・水道負担金などです。
水道を使用する人、上水道の径を太くしようとする場合などにかかります。
市町村によって異なるので、一概には言えませんが、下水道使用料などを請求される市町村もあります。
そもそも、前面道路に下水道が通っていない地域もありますから、居住される市町村によって異なります。
厳密には税金ではないのですが、公的機関が提供するサービスなので、このカテゴリに入れました。
業者に支払うカテゴリ
次は家づくりに関わる各種業者に支払うカテゴリです。
不動産業者への仲介手数料
土地を購入する場合、その土地を仲介した不動産業者に仲介手数料を支払います。
その不動産の代金の3%+6万円に消費税です。
これは分譲マンションでも、建売住宅でも、不動産なので同じです。
不動産業者への仲介手数料がかかります。
司法書士報酬
司法書士報酬は前述した登記の手続きを代行してもらう報酬です。
登記手続きは司法書士の独占業務です。
司法書士報酬の金額は各司法書士によってまちまちです。
代行費用ですね。
土地家屋調査士報酬
土地家屋調査士報酬は住宅(建物)を表示登記(建物が建った旨の登記)をする際にかかる費用です。
また、すでに土地を持っていて、その土地の測量をきちんとしたかったり、
近隣との境界を確定させようと思った場合、土地家屋調査士に依頼することになります。
その際に、土地家屋調査士に支払う報酬になります。
引っ越し費用
引っ越し費用はわかりやすく、引っ越し業者に支払う費用です。
結局は引っ越しするときの荷物の量によって金額は変わります。
家具などの荷物が少なければ、安いですし。
荷物の量が多ければ、高いです。
量が少なければ、自分でやることもできます。
金融機関カテゴリ
次は金融機関に支払う費用カテゴリになります。
融資手数料
住宅ローンを借りる際に、融資手数料としてお金を支払います。
「お金を借りるのに、お金がかかるのか?」
と思われるかもしれませんが、現実としてお金を借りるのにお金がかかります。
住宅ローンをどこから借りるかで金額は変わります。
住宅ローン保証料
住宅ローン保証料とは、住宅ローンを組むときに、保証会社による保証制度を利用する費用です。
保証会社は地方銀行の場合、銀行子会社であるケースが多いです。
もしくは、共同出資とか。
保証されないと住宅ローンを組めません。
住宅ローン保証料は借り入れ金額と返済期間によって異なります。
「住宅ローン保証料はなし」という場合は、住宅ローン金利に上乗せされているケースです。
団体信用生命保険料
団体信用生命保険料とは、住宅ローンの返済中に借り手が死亡したり、高度障害(死亡とほぼ同じ)になった場合、残りの住宅ローン(残債)を完済する保険を団体信用生命保険と言いまして、その保険料になります。
借り手からしますと、住宅ローンを組んでいる人が亡くなった場合、
住宅はそのまま所有できて、借金はチャラということになります。
現実としては、この制度は貸し手目線でして。
住宅ローンを返済しているときに、返済者である借り手に死なれると、どうなりますでしょうか?
それは借金返済できなくなってしまうので、取りっぱぐれてしまいます。
貸し倒れです。
貸し倒れリスクはゼロにしたい。
もちろん、土地・建物は抵当にとってありますから、競売などで現金化はできます。
ただ、残債が大きい場合、競売で現金化したとしても、全額回収できるとはかぎりません。
そもそも、競売は手間が非常にかかりますから、面倒です。
そういうわけで、借り手の死亡リスクに対処すべく、死亡保険に入っていただきたいと考えております。
そのような流れで、団体信用生命保険に加入することを住宅ローンでは義務づけられております。
まあ、お互いのためですね。
民間金融機関の場合、団体信用生命保険料は金利に含まれているケースが多いので、支払い負担を感じることはないかもしれません。
フラット35とかですと、別途支払うことになりますから、負担感があるかもしれません。
ただ、どちらにせよ、この保険料は支払っています。
その他カテゴリ
あとは、その他カテゴリとして、諸費用についてまとめます。
火災保険料・地震保険料
火災保険料・地震保険料とは、その名前からおわかりの通り、一般的な火災保険料と地震保険料です。
住宅が火災で被害を受けたら、保険金がおります。
地震で被害を受けたら、金額がうんぬんありますが、保険金がおります。
ほとんどの住宅ローンでは、火災保険の加入が義務づけられています。
なので、火災保険に入らないといけません。
この火災保険料が諸費用に入ります。
ちなみに、これも住宅ローンの貸し手側目線のリスクがありまして。
住宅が火事にあって、火災保険入ってなかったら、どうなりますでしょうか?
住宅は火事で燃えてない。
住む場所はない。
でも、住宅ローンの返済は消えない。
これって、まずい状況ですよね。
借り手もそうですが、貸し手もそうなんですよ。
仮住まいでもいいんですが、住居費が二重でかかります。
そうなると、住宅ローンの支払いができないリスクがあります。
ですから、火事になったら火災保険で住宅ローンが支払ってもらえるように、
火災保険には入っていないと、住宅ローンを貸さないようにしています。
まあ、お互いのためですね。
家具・家電の購入費用
住宅を新築しますと、家が新しくなっていますから。
「せっかくだから、家具も新しいものにしよう!」
「家電も新しくしよう!」
そう考えるのは不思議ではありません。
たいていは、そう考えます。
ですから、そのほかにかかる費用として、家具・家電の購入費用が入ります。
新しい家具はそれこそピンキリですから、ご家族によって費用は異なります。
家電についても、同じですね。
ご家族によって、グレードも違いますし。
まとめ
このように、諸々の費用ということで、諸費用となります。
たくさんありましたね。
「こんなにいっぱい、土地・建物以外にお金払うの??賃貸がいいや」
って、一瞬でも思いませんでしたか??
でも、賃貸も、賃貸オーナー・大家さんは同じような諸費用を負担しているんですよ。
特に不動産取得税なんかは、自己居住目的の場合、
つまり、新しい家づくりをしようという方には軽減措置ありますが、
不動産賃貸業の物件の場合、それはないです。
負担が意外に大きいんです。
それで、不動産賃貸業していますから、どういう意味かわかりますよね?
その賃貸の賃料には、それが含まれているって意味です。
諸費用はたしかに種類も多く、それなりに高額になります。
ただ、実際にはそれは見えないかたちですが、
賃貸住宅に住んでいる以上、含んだかたちですでに賃料負担しているのです。
ですから、諸費用も逃れられない費用ということで、
前向きにとらえていただいて、資金計画に入れられることをおすすめいたします。
家づくりにかかるお金のことをすべて把握された上で、
満足のいく幸せな家づくりをされますことを願っております。
ご家族が
幸せに暮らすことのできる
家づくりを。
何かお知りになりたいことあれば、
お気軽にご相談予約ください。
「住宅ローンについて、借りる前に知っておきたいことまとめ」というテーマで、記事をまとめています。
一通りご覧いただき、興味のあるところを読み進めていただけましたら、ご参考になると思います。