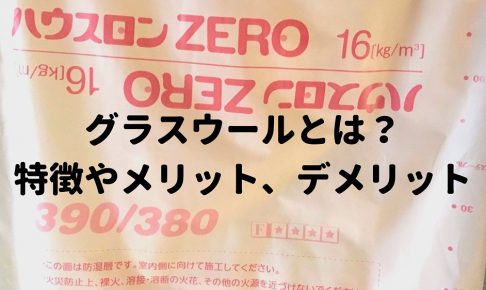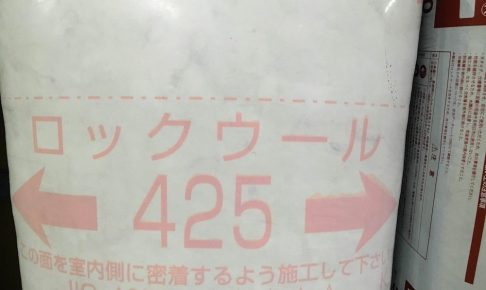- 「断熱材が気になります。詳しく知りたい」
- 「どんな断熱材の種類があるのか、知りたい」
- 「自分の家にぴったりの断熱材はどれか検討したいです」
この記事ではこのような疑問にお答えします。
今回の記事では「断熱材とは?種類や選び方で、家の快適性が変わる?【プロが解説】」というテーマでお伝えします!
断熱材とは?
断熱材とは熱移動を減少させる資材のことを指します。
「熱」を「断」つ、資「材」ということで、断熱材と呼びます。
建築用のものは断熱材、工業用のものは保温材と呼ばれることが多いです。
住宅建築においては、住宅全体の室内空間の温度を一定に保つため、外からの温度の影響を減らすために用いられます。
つまりは夏に涼しく、冬にあたたかい住宅にする目的です。
断熱の意味は?
では、注文住宅において「断熱」はどのような意味があるのでしょうか?
端的に言えば「夏涼しく、冬あたたかい」家を実現するという意味です。
断熱によって、快適性がアップするということです。
「断熱」の基本的な意味は、その文字の通り「熱」を「断」つ、という意味になります。ですから、外の温度と内の温度を断つことになります。
元々、かつての住宅は建売(分譲)住宅でも、注文住宅でも、あまり断熱化がなされていませんでした。
外側と内側とで熱が断たれていないので、外が寒いと家の中(内側)にいるにもかかわらず、寒いということになります。
そういうわけで、冬の季節ではリビングダイニングは暖房でガンガンにあたためなければなりませんでした。あたためる方法も、ガスファンヒーターのようなヘビーな暖房方法を選択する必要がありました。
廊下は寒く、居室も寒いので、暖房をかけ続けていないといけませんでした。
夏は外が暑いので、家の中も暑い。
クーラーでキンキンに冷やして、ようやく涼しい感じになります。
家が快適になるのも、不快になるのも、断熱性しだい
こうして、家が不快になってしまう理由は断熱性の低さになります。
一方で、家を快適にするには断熱性を高くすればよいということになります。
断熱性が高い住宅だと、熱が遮断されるので、外が寒くても、家のなかはあたたかいです。夏は外が暑くても、家のなかは涼しいです。
断熱性が高いと、家全体が温度差があまりなくなるので、全館快適、家のどこにいても快適になります。
断熱性が低いと、寿命も短くなる?!
前述したように、断熱性が低いと、温度差がひどくなりますから、寿命が短くなるリスクも出てきます。
どういうことかと言いますと、冬場で部屋を暖房でたっぷりあたためた状態で生活していた場合。
廊下に行けば寒い。風呂場に行けば、凍えるような寒さ。風呂場で凍えるような寒さの状態で、裸になってお風呂へ。
この温度差が人体に悪いです。
俗にいう「ヒートショック」が起こります。
急激な温度差が体にダメージを与えるわけです。
お年を召された方は脳溢血などを引き起こし、ひどい方は亡くなられるケースもあります。
これが断熱性が高い住宅であれば、変わります。
断熱性が高いと、熱が遮断されるので、外が寒くても家のなかはあたたかいです。家全体でも温度差があまりありません。
リビングダイニングも、廊下も、お風呂場も、さして温度差がないのでヒートショックも起こりません。
断熱は、節電や地球温暖化対策にもつながる
また、高い断熱性の住宅は節電や地球温暖化対策にもつながります。
それはエネルギーをあまり使わなくても、快適な温度に保てるからです。省エネ住宅です。
家庭からの二酸化炭素が発生する原因は一番が電気です。二番はガソリンです。
それで一番使う電気の中で、最も電気を使うのが「エアコン」です。25.2%を占めているそうです。
電気を使う目的は温度調節するため、というのがエアコンですから、断熱性が高い住宅であれば、そこまでエアコンを使わずに温度調整できます。それが節電であり、省エネであり、二酸化炭素の発生を減らす効果があります。
また、省エネ・節電できることで、光熱費を減らすことになります。生活費が浮くわけです。
断熱材の種類
それでは、現在の注文住宅業界において、どのような断熱材が使用されているのでしょうか?
断熱材の種類は2種類に大別できます。
「繊維系断熱材」と「プラスチック系断熱材」です。
それぞれ、個別の種類に分けると以下のようになります。
繊維系断熱材の種類
繊維系断熱材の種類は下記になります。
- グラスウール
- ロックウール
- セルロースファイバー
プラスチック系断熱材の種類
プラスチック系断熱材の種類は下記になります。
- ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)
- 押出法ポリスチレンフォーム(XPS)
- 硬質ウレタンフォーム
- フェノールフォーム
ちなみにここで7種類の断熱材をご紹介していますが、実際にはもっとたくさんの種類の断熱材があります。
たとえば、「繊維状ポリエステルの断熱材」「インシュレーションボード」「羊毛断熱材」などです。
グラスウール

グラスウールとは、ガラス(グラス)をウールのように細い繊維状に加工した断熱材です。
在来木造軸組工法で一戸建てを新築した場合、一般的に用いられる断熱材がこのグラスウールです。
床、壁、天井などと住宅のほとんどの部位の断熱に使用できます。
無機質なので不燃材です。吸音性能や耐久性にも優れています。
湿気には弱いです。
ロックウール
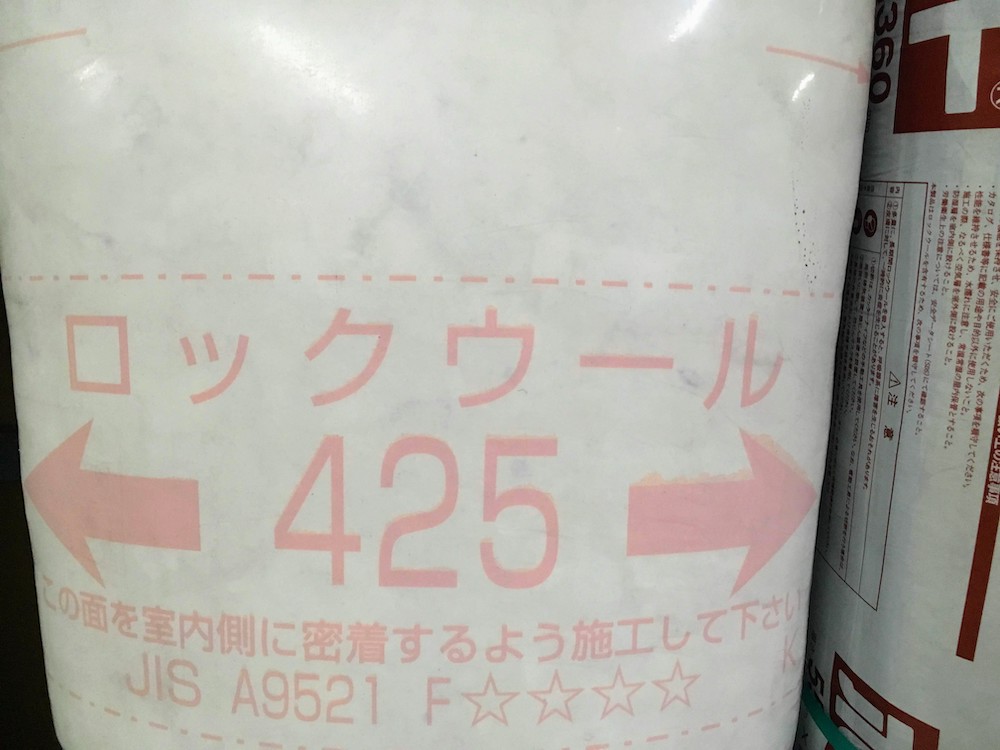
ロックウールとは玄武岩、その他の天然岩石などを主原料として、1,500~1,600℃の高温で溶融するか、製鉄所の高炉から出た溶融スラグを電気炉で1,500~1,600℃の高温で溶融して、遠心力などで吹き飛ばして繊維状にした人造鉱物繊維のことを指します。
ロックウールは名前としては岩をウール(繊維)状にしたものという感じですが、日本で流通しているロックウールは別名・スラグウールと呼ばれるように、製鉄所の高炉から出た溶融スラグを繊維状にしたウールになっています。
床、壁、天井などの住宅のほとんどの部位の断熱に使用できます。
石綿と字が似ていますが、0.3ミクロン程度の極細繊維である石綿とは基本的に異なります。
セルロースファイバー

セルローズファイバーとは、天然の木質繊維を利用したばら状断熱材です。
木質繊維系断熱材です。
新聞の古紙がよく用いられます。断熱性、防音性があります。
ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)

ビーズ法ポリスチレンフォームとは発砲プラスチック系断熱材の一種です。
「Expanded Poly-Styrene」の頭文字をとって「EPS」とも呼ばれます。いわゆる発砲スチロールです。
一つ一つの粒の中に独立した気泡構造を持ったボード状の断熱材です。
水や湿気に強いです。軽く、加工性、施工性に優れています。
押出法ポリスチレンフォーム(XPS)

押出法ポリスチレンフォームとは、ポリスチレン樹脂に炭化水素などの発泡剤を加えて押出成形された断熱材です。
断熱材を建物の外側に張りつける外断熱工法に適したボード状の断熱材です。水に強く、断熱性に優れています。
薄くても断熱効果が高く、施工後の重量も軽くすることができます。
水に強く、耐湿性があるため、基礎や土間床の断熱にも使用できます。
ポリスチレンフォームの2種類(EPSとXPS)の違い
上記2つのポリスチレンフォームはイメージとしては、発泡スチロールです。
冷凍品、冷蔵品などを入れる発泡スチロールの箱はなぜ、保冷用に使われるのでしょうか?
それは断熱性が高い素材だからです。
住宅の建材としても、使われているわけです。
発泡スチロールとは合成樹脂素材の一種で、気泡を含ませたポリスチレンのことです。スチロールはスチレンの別名です。
上記2つの「ビーズ法ポリスチレンフォーム」と「押出法ポリスチレンフォーム」の違いは製法の違いです。化学的にはほぼ同じですが、形状や気泡の特性が違います。
ビーズ法ポリスチレンフォームの製法は「ビーズ」と呼ばれる小さなポリスチレンの粒を発泡させるというものです。
直径1mm程度のポリスチレンビーズにブタン・ペンタンなどの炭化水素ガスを吸収させ、100度以上の高温蒸気を当てます。樹脂を軟化させると共に圧力を加えて発泡させます。
発泡したビーズ同士は融着し合い、冷却した後、ポリスチレンフォームとなります。容積の95%は炭化水素ガスです。
押出法ポリスチレンフォームの製法は液化した原料を吹き出すことで製造するものです。
液化した原料と発泡剤、難燃剤を高温・高圧下でよく混ぜ、一気に通常気圧・温度の環境に吹き出します。連続的に発泡、硬化させ、必要な大きさの板に切断します。
硬質ウレタンフォーム
硬質ウレタンフォームとは、ポリウレタン樹脂が主成分の発泡させたスポンジ状の断熱材です。
微細な独立気泡で形成されています。その気泡で断熱します。
フェノールフォーム
フェノールフォームとは非常に安定した分子構造をもつフェノール樹脂を主原料にした断熱材です。
素材の安定性が高く、長期間にわたって優れた断熱性能を発揮します。
フェノール樹脂は熱硬化性樹脂で130度までの使用に耐える耐熱性があり、防火性にも優れています。
一番有名なフェノールフォーム断熱材は旭化成建材の「ネオマフォーム」です。
断熱の仕方(工法)の2種類:充填断熱と外断熱
また、断熱材の種類と同時にそれらをどのように施工するのか、という断熱の仕方(工法)にも2種類あります。
具体的には「充填断熱工法(内断熱)」と「外張断熱工法(外断熱)」です。
充填断熱工法(内断熱)の特徴
充填断熱工法(内断熱)とは壁内の柱・間柱、梁など軸組み間の空隙に断熱材を施工する方法のことです。
特徴は下記の通りです。
- 充填断熱工法は壁内で断熱するため、断熱材を施工しても、壁が厚くはならない
- 主に繊維系断熱材が用いられますが、プラスチック系でもOK
- 気密を取りづらいので、施工が問題になる
- 隙間に断熱材を充填(はめこむ)するので、柱との間に隙間ができないようにする必要がある
- 断熱材の保管時や施工時に水濡れに注意が必要
外張断熱工法(外断熱)の特徴
外張断熱工法(外断熱)とは、柱・間柱、梁など軸組みの外側に断熱材を施工する方法のことです。
特徴は下記の通りです。
- 軸組みの外側に断熱材を施工するため、壁厚が増します
- 外張断熱工法(外断熱)には、主にボード状の発泡プラスチック系断熱材が使用されます。ボード状の繊維系断熱材が用いられる場合も。
- 気密化しやすいので、施工が容易
- 外側に壁厚が増すため、サッシ固定枠を壁外側に別途設けなければなりません
- 施工の都合上、あまり厚くすることもできず、厚みが薄いため性能的には微妙になることも
- コストが高い
断熱材の選び方
ここからは断熱材の選び方についてお伝えします。
基本的には3つのポイントがあります。
- 湿気に強いかどうか
- 施工時に気密が取れるかどうか
- コスト(お金)の問題
湿気に強いかどうか
断熱材の素材が湿気に強いかどうかがポイントのひとつです。
なぜ、湿気に弱いといけないか、というと、壁のなかでも外でもいいのですが、日本の気候はじめっとした湿度の高い環境です。そのため、その湿気に触れて弱いとなると、断熱材の効果が弱まってしまうからです。
湿気に弱い断熱材でも、きちんとビニールシートなどでカバーすることで、湿気が入らないようにする対策によって、使用可能になります。ただ、その施工をきちんとしていれば、の話ですので、すべてにおいてそれがきちんと施工されているわけではないです。
そういうわけで、断熱材そのものが湿気に強いものであれば好ましいというわけです。
具体的にはプラスチック系断熱材は全般的に湿気に強いです。
意外なところで、セルロースファイバーも湿気に強いです。木質繊維なので、湿気を吸放湿するからですね。
グラスウールとロックウールは湿気に弱いです。
施工時に気密が取れるかどうか
高気密高断熱住宅という呼称でわかりますように、単に断熱性が高いだけでは不十分です。高気密である必要があります。
それは気密性が低いと、空気で熱が移動してしまう、逃げてしまうからです。
そういうわけで、施工時に気密が取れるかどうかがポイントになります。
基本的に外断熱であれば、施工時に気密を取りやすいです。プラスチック系断熱材で、外断熱であれば気密はOKでしょう。
充填断熱は気密がとりにくいのですが、施工をきちんとしていれば問題ないです。
まあ、ここのところは施工会社の住宅会社・工務店の施工に対する姿勢で変わりますので、なんとも言えません。
コスト(お金)の問題
最後はコスト(お金)の問題がポイントになります。
一般的にプラスチック系断熱材は高価です。
反対に、繊維系断熱材は安価であることが多いです。
セルロースファイバーは比較的お高めです(色々とメリットが多いですし、施工で気密がとれやすいので)。
結局はコストパフォーマンスということになりますが、依頼先の施工会社(住宅会社・工務店)の慣れた断熱材が好ましいというケースが多いかもしれません。
高気密高断熱住宅の住まい方・住む上での注意点
このように、きちんと断熱材で施工された高性能な家のことを「高気密高断熱住宅」と呼びます。
ここでは、そんな高気密高断熱住宅の住まい方・住む上での注意点をまとめます。
開放型ストーブは使用しない
開放型の石油ストーブ、ガスストーブ、開放型の石油・ガスファンヒーターは燃焼ガスを室内に放散します。
高気密高断熱住宅は名前の通り、気密が高いので一酸化炭素中毒になるリスクが起こります。
もちろん、換気を多くすれば問題ないのですが、省エネ効果は低下します。
ですから、暖房には燃焼排ガスを屋外に排出する、室内の空気を汚さない器具を選ばれることをおすすめします。
たとえば、密閉型暖房機、FF式温風暖房機、電気ストーブ、エアコン、セントラルヒーティングなどです。
換気装置は止めない
換気装置(計画換気システム)は常時運転させます。
台風のときは例外的に止めたほうがいいです。それ以外は常時運転させます。
換気システムが止まると、空気質の悪化、結露が起こる可能性があります。
停電や故障など万一、換気装置が作動しない場合は、窓を開けて自然換気を行います。
ガスレンジ使用時には強制換気する
ガスレンジなどを使用する時は必ず換気扇(レンジフード)を使って強制換気します。
上述と同じ理由で、高気密高断熱住宅は気密が高いです。
そのため、酸欠や一酸化炭素中毒のリスクが起こります。
人が大勢集まった時には換気量を増やす
室内に大勢の人が集まった時などは、換気量が不足しがちです。
強制換気を行うか、窓を開けて自然換気を行います。
換気装置をこまめに掃除する
換気装置の給気口と本体のフィルターは、定期的に掃除します。
給気口のフィルターにはゴミやほこりが溜まります。
定期的に掃除をしないと、必要な換気能力が発揮できなくなります。
外部に面した壁に穴あけるとき、増改築のときは相談する
高気密高断熱住宅の壁内部は断熱・気密をきちんととるために配慮されて施工されています。
深い理解のないまま、エアコン取付工事などで壁に穴をあけてしまうと、せっかくの性能を損なってしまいます。ぶちこわしです。
外部に面した壁に穴をあけるときや、増改築の際には建設した業者に相談することをおすすめします。
まとめ
ここまでお話してきた内容をまとめると、次の4つのポイントになります。
- 断熱材の種類はたくさん(7種類以上)あり、どれも注文住宅に使われている
- どの断熱材も適切に施工されれば、きちんと機能する
- ハズレがないのは外断熱の断熱材(プラスチック系)だが、コストが高く、厚みが薄いので性能が高くない
- 施工で当たりはずれがあるのが内断熱(充填断熱)の断熱材(繊維系断熱材)だが、コストは安めで、厚みが確保できるので性能が高くなりやすい
以上です。
家づくり、断熱材選びの参考になりましたら、幸いです。
関連記事
- 【注文住宅】注文住宅の家づくりで知っておくべきこと
- 【間取り】理想の間取りはどうつくる?
- 【住宅設備】理想の住宅設備で、快適な生活を送るには?
- 【長持ち快適おしゃれ】長持ち、快適、心地いい、おしゃれな家のコツ
- 【お金・予算】家づくりのお金。いくらかかる?いくらかける?
- 【細かいポイント】細かいけど、知っておきたい家づくりの知識